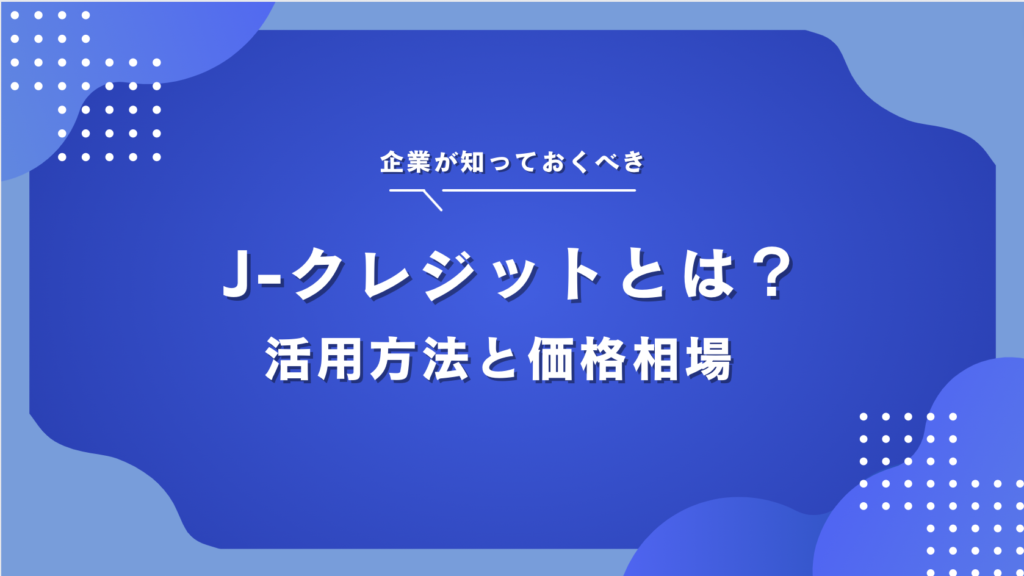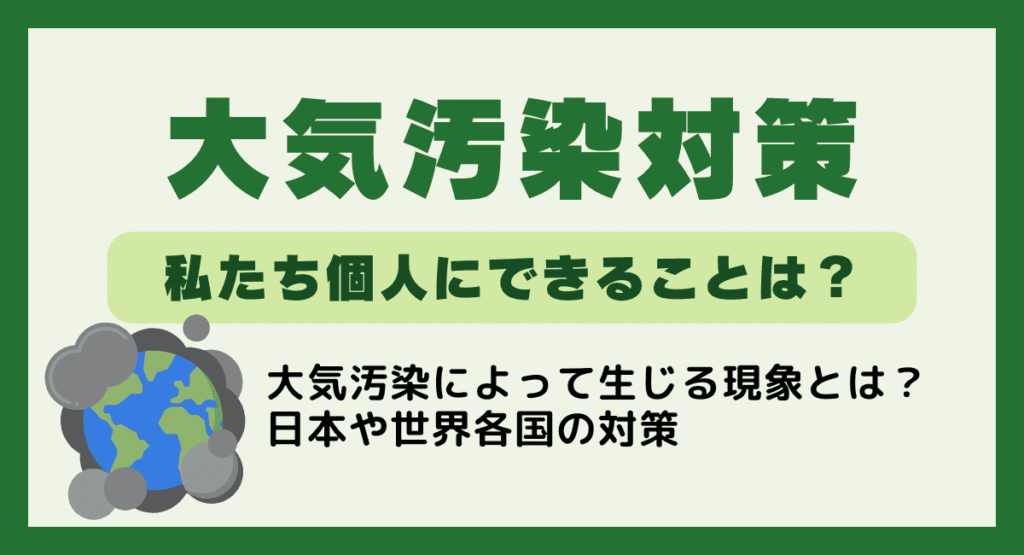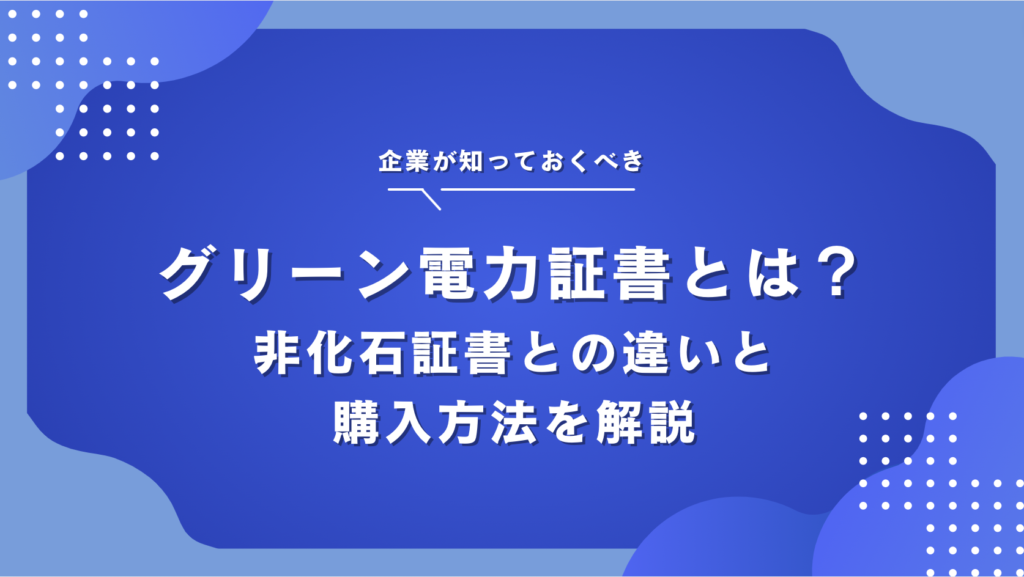ゼロエミッションとは?カーボンニュートラルとの違いと注目されている背景、日本企業の取り組み具体例
- CO2削減
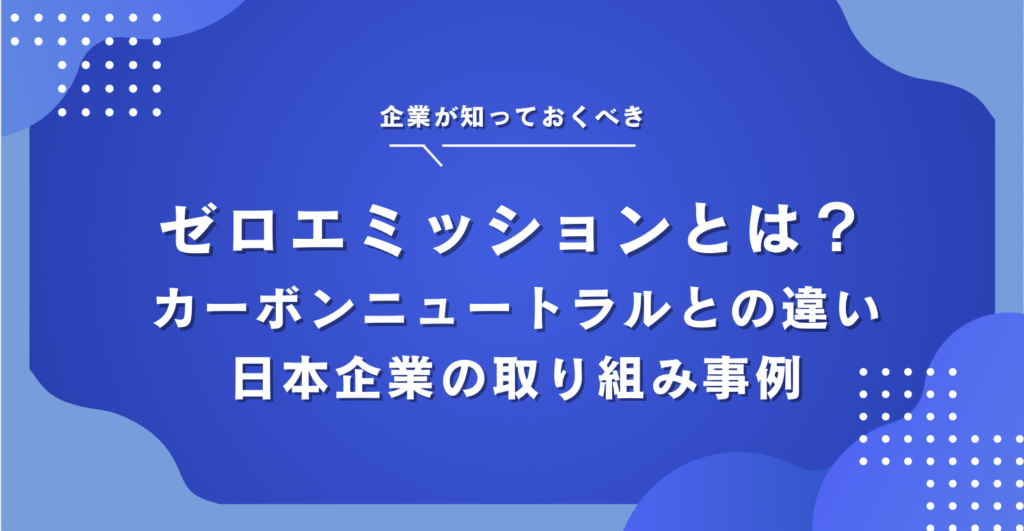
廃棄物と温室効果ガスをゼロにすることを目指すゼロエミッションへの取り組みが注目されています。世界と日本の政府はゼロエミッションに向けてどのような活動をしているのかを見てみましょう。
カーボンニュートラルやネットゼロとの違いや取り組むメリット、日本企業の取り組み事例と企業が取り組む方法などもあわせてご覧ください。
目次
ゼロエミッションとは
ゼロエミッション(エミッション=排出)は「人間の活動の過程で自然界に排出される廃棄物や温室効果ガスをゼロにする」という目的を指します。1994年にUNU(国際連合大学)の学長顧問であるグンダー・パウリ氏が提唱して世界に広がりました。ゼロエミッションの試み・理念・目標は以下の通りです。
| 試み | 人間の産業や経済活動で生じる廃棄物などが自然界に排出されないように努める |
| 理念 | 廃棄物をゼロにするだけを目的とせず、廃棄物に付加価値を見出して限界まで利用する |
| 目標 | 廃棄物の再利用・有効活用によって廃棄物を減らすため、産業界と経済界はサーキュラーエコノミーに基づいた経済を構築する |
上記の取り組みは温室効果ガス削減にも効果を発揮するので、近年は「CO2実質排出ゼロ」や「温室効果ガス排出ゼロ」という取り組みにもゼロエミッションの指標が使われています。
ゼロエミッションとカーボンニュートラルの違い
ゼロエミッションとカーボンニュートラルは「温室効果ガスをゼロに」という目的が一致していることから混同されがちですが、厳密には異なります。2つの違いを表に示します。
| 名称 | 目的 |
| ゼロエミッション | CO2などの温室効果ガス・廃棄物・海洋汚染物質・大気汚染物質などを排出しないことでゼロに近づける |
| カーボンニュートラル | CO2などの温室効果ガスの排出量と吸収・削減量を差し引きゼロにする |
「ゼロに近づけるために排出しない」と「排出するが吸収・回収・削減も行ってプラスマイナスゼロにする」という点で異なりますが、ゼロエミッションはカーボンニュートラルを達成するために必要な手段として注目され、世界各国の政府・自治体・企業が実施しています。
ゼロエミッションとネットゼロの違い
ネットゼロは、温室効果ガスの排出量を正味ゼロにすることを表します。
カーボンニュートラルとネットゼロは同じ意味で用いられますが、カーボンニュートラル・ネットゼロとゼロエミッションの意味は違います。
カーボンニュートラルとネットゼロは温室効果ガスが実質ゼロになった状態を指し、ゼロエミッションはカーボンニュートラル・ネットゼロを実現するための活動を指す言葉なのです。
ゼロエミッションはなぜ注目されているのか?
産業革命以降、経済発展の過程でそれまでとは比較にならないほどの温室効果ガス・廃棄物が生じるようになり、世界中で地球温暖化による異常気象などが頻発するようになりました。
ゼロエミッションは、「カーボンニュートラルを達成することで地球温暖化を食い止めよう」「地球の自然環境を守ろう」という機運が高まる中で、注目度が上昇してきています。
廃棄物を減らす・廃棄物の再資源化を進めるなどの活動に世界各国の政府・企業が取り組むことで、温室効果ガスの排出量を減らし、カーボンニュートラル達成という目標に近づくと共にゼロエミッションも実現できるからです。
これまでは大企業のゼロエミッションに向けた活動が目立ちましたが、近年は中小企業の活動報告も増えています。
ゼロエミッションに取り組むメリット
廃棄物・温室効果ガスをゼロにするという活動への取り組みには、以下のようなメリットがあります。
- 気候変動の緩和
- 取り組みによる投資効果
世界中で異常気象やそれによる災害が報告されているここ数年の情勢を見ると、ゼロエミッションに取り組むことで気候変動を緩和できるというメリットが非常に大きいことがわかります。
また、取り組む自治体や企業に政府・金融機関・投資家が投資を行うという恩恵も期待できます。アメリカでは、バイデン政権がゼロエミッションのための活動に巨額の投資を実施しました。
世界と日本のゼロエミッションの現状
世界各国が、カーボンニュートラルや温室効果ガス削減につながるゼロエミッションに取り組む姿勢を示しています。世界と日本における現状・取り組みを見ていきましょう。
世界の現状と取り組み
世界では、この項で紹介する戦略や同盟などを設立してゼロエミッションに取り組んでいます。
First Movers Coalition(FMC)の立ち上げ
2021年10月末から11月上旬にかけてイギリス・グラスゴーで開催されたCOP26(国連気候変動枠組条約第26回締約国会議)において、アメリカ政府と世界経済フォーラムが協力して立ち上げたイニシアティブがFirst Movers Coalition(FMC)です。2050年までのネットゼロ達成を主目的に掲げ、必要な重要技術の市場創出を早期に実現させることや脱炭素技術の開発・普及促進を目指し、世界の主要企業が購入をコミットするプラットフォームとして成立しました。
2021年4月発表の日米気候パートナーシップに基づいて協力した結果、日本政府も2022年5月に戦略パートナー国としてFMCに参画することを表明し、2022年7月までに55社が参加しています。
(参考:経済産業省「「First Movers Coalition(FMC)」に戦略パートナー国として参画します」)
日EUグリーンアライアンスの合意
日本とEUの間では日EUグリーンアライアンスが合意されました。
日EUグリーンアライアンスでは、日本とEUで2050年カーボンニュートラルとグリーン成長を実現するため、気候中立で生物多様性を考慮した資源循環型経済の実現を目標に掲げています。協力内容を以下に示します。
| エネルギー移行 | 再エネ・蓄電池・水素・CCUSやカーボンリサイクルなどの技術協力 |
| 自然環境保護 | 資源循環効率の向上・生物多様性保全 |
| 民間部門支援 | 企業の気候変動対策・環境配慮の推進に資する政策推進 |
| 研究開発 | 低炭素技術研究開発・社会実装 |
| 持続可能な金融 | 持続可能な金融制度構築に向けた金融基準策定 |
| 第三国協力 | 途上国の気候変動対策支援促進 |
| 公平な気候変動対策 | 日EUの取り組みが正当に評価される国際ルールの整備・主要新興国への共同での働きかけ実施 |
アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)の開催
2023年3月、日本・経済産業省がアジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)閣僚会合を東京都内で開催しました。
参加したのはインドネシア・オーストラリア・カンボジア・シンガポール・タイ・フィリピン・ブルネイ・ベトナム・マレーシア・ラオスと日本です。
西村経済産業大臣が議長を務め、アジアの脱炭素の重要性やAZECの構想と日本の具体的取り組み内容について発言し、各国の参加者と意見を取り交わしました。AZECの概要は以下の通りです。

(出典:経済産業省「カーボンニュートラル実現に向けた 国際戦略」)
会合では以下3つの共同声明が合意され、AZECの枠組みとして立ち上げられています。
- 脱炭素とエネルギー安全保障との両立を図ること
- 経済成長を実現すると共に脱炭素を推進すること
- カーボンニュートラルに向けた道筋は各国の実情に応じた多様・現実的なものであるべきこと
(参考:経済産業省「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)閣僚会合及びAZEC官民投資フォーラムを開催しました」)
日本の現状と取り組み
ゼロエミッションの日本国内の現状と実施している取り組みをご覧ください。
水素エネルギーの利用
水素を「ゼロエミッション達成に不可欠なエネルギー」と認識している日本では、ゼロエミッションが推進される前から水素エネルギーが研究されていました。燃料資源が群を抜いて少ない日本では、化石燃料に代わる資源として注目され続けていたのです。
日本では、ゼロエミッションとカーボンニュートラルを共に実現できる水素エネルギーを2030年に社会実装することを目標に、水素エネルギーの研究開発とインフラ整備、水素供給サプライチェーン構築などに取り組んでいます。
カーボンリサイクル
回収したCO2を資源として活用するカーボンリサイクルも、ゼロエミッション達成に必要な技術です。
日本ではCO2を原材料とするコンクリート・燃料などの研究・開発・実証実験を進めています。カーボンリサイクルの技術は極めて重要なCO2の削減手段なので、政府と企業と研究機関などが連携して生産性向上・コスト削減を目標に推進しています。
また、カーボンリサイクルに関連した研究拠点を全国に展開し、CO2の回収・貯留技術の実証実験や、化石燃料に頼らない水素の製造実証事業などを実施中です。
カーボンリサイクル製品で特に注目されているのはCO2吸収型コンクリートで、このコンクリートを含むカーボンリサイクル技術の社会実装とコストダウンを図ると共に、海外へ広げようとしています。
ゼロエミ・チャレンジ
経済産業省は、2020年に経団連・NEDOと連携してゼロエミ・チャレンジを発足しました。
2050年カーボンニュートラル実現に向けたイノベーションにチャレンジする企業をリスト化し、リスト化された企業が投資家・金融機関から資金を集めやすくするプロジェクトです。
イノベーションに取り組む企業をゼロエミ・チャレンジ企業と位置づけ、2020年10月のTCFDサミット2020の席上で、NEDO実施の28プロジェクトのみが対象の企業リストと「革新的環境イノベーション戦略」に関連した経済産業省の事業を公表しました。
2021年10月のTCFDサミット2021では、上場・非上場企業の合計600社以上のゼロエミ・チャレンジ企業を発表しています。
(参考:経済産業省「ゼロエミ・チャレンジ」)
日本企業のゼロエミッションの取り組み事例
日本や世界各国の企業もゼロエミッションを実施しています。ここでは日本企業がゼロエミッションにどう取り組んでいるかを解説します。
企業の取り組み事例①旭化成株式会社
旭化成は自社サイトで社会問題への取り組みを7つに分類して紹介しています。そのうちゼロエミッションに該当するのは「100年後の暮らしを守る取り組み事例」で、廃棄プラスチックなどを削減するための仕組みの具体例を公開しています。
| 製品名 | 取り組み | 成果 |
| サランラップ | 製造工場において工程排出物削減/産業廃棄物の再生利用・熱回収 | 2015年度に最終埋立処分量ゼロ達成 |
| ジップロック | 使用済ジップロックを集めて別のプラスチック製品にリサイクル | ジップロップバッグをシートに作り替えて傘を製作してシェアリングサービスで活用/ジップロックコンテナのリサイクル素材を使用したゴミ拾いトング製作 |
また、循環型社会への取り組みでは、2003年度から推進している3R(リデュース・リユース・リサイクル)により、最終埋立処分量をゼロにするゼロエミッションを達成し、以降も継続しています。
具体的には、生産と調達計画の綿密な連動で原料・資材の工場受け入れに無駄が出ないよう手配し、作業工程で出た廃棄物の再使用・再生利用を実施中です。
(参考:AsahiKASEI「廃棄プラスチック削減のための仕組みづくり」)
(参考:AsahiKASEI「サステナビリティ」)
企業の取り組み事例②アサヒビール株式会社
アサヒビールは、1998年11月に工場の作業工程で出た廃棄物の再資源化100%を全工場で達成しました。
アサヒビールとニッカウヰスキー全工場のビール・発泡酒の生産過程で出る副産物・廃棄物は年間約37万tに及びますが、その全てを再資源化・再生利用しているのです。具体例は以下の通りです。
| 副産物・廃棄物 | 再利用方法 |
| モルトフィード | 家畜の飼料など |
| 汚泥 | 有機肥料・堆肥 |
| アルミ屑 | アルミ缶・電気製品 |
| ガラス屑 | 瓶の材料・建材 |
| ビール酵母 | グループ企業が販売している医薬品・加工食品の原材料 |
従業員に廃棄物の分別について「廃棄物の分別ではなく資源の分別をしている」という意識を持たせるなどの教育を徹底した結果、再資源化100%が実現しました。
(参考:JFS「廃棄物再資源化100%を達成したアサヒビール」)
(参考:Asahi「持続可能な資源利用」)
企業の取り組み事例③住友林業株式会社
住友林業グループは、各事業所から出る全ての産業廃棄物の単純焼却と埋立処分を行わない「リサイクル率98%以上」をゼロエミッション達成と定義しています。
2009年度に国内製造工場、2012年度に首都圏エリアの新築現場でのゼロエミッションを達成させました。2020年度には海外製造工場でゼロエミッションを達成させています。
事業活動内容を、新築現場・国内製造工場・発電事業・リフォーム事業・生活サービス事業など・海外製造工場・解体工事現場の7区分に分けた上で従来よりきめ細かな管理を行い、2021年度・2022年度に国内製造工場・海外製造工場・発電事業でゼロエミッションを実現させました。

(出典:住友林業「資源循環への取り組み」)
廃棄物管理者の知識習得・プラスチック対応基準の策定・プラスチック資源循環促進法対応なども実施しています。その結果、上表で示すように廃棄物発生量の減量とリサイクル率の向上を実現しています。
(参考:住友林業「資源循環への取り組み」)
企業がゼロエミッションに取り組む方法・具体例
今後ゼロエミッションに取り組みたい企業がどういった活動から着手するべきかを解説します。取り組み方と具体例をおさえておきましょう。
省エネ
取り組む方法の中で特に手軽に始められるのは省エネです。省エネなら温暖化問題がなくてもすでに実施している企業が多いのではないでしょうか?
資金面でゼロエミッションを実施するのが難しい中小企業でも、短期的・中期的な省エネ対策を考案した上で省エネを推進していくことが可能です。資金繰りに苦しんでいるなら、経費節減という点で省エネが企業の危機を救う手段になり得るからです。
より高効率かつ環境に優しい再生可能エネルギー電力に切り替えることでも省エネにつなげられます。初期投資は必要ですが、長期的に見れば現状よりも経営が安定する可能性が高く、再生可能エネルギー導入で税制優遇や補助金の恩恵を受けられます。
カーボンニュートラルも含めて念頭に入れた上で、短期・中期・長期に分けて綿密な事業計画を立てて省エネを実施しましょう。
ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業
省エネ設備の導入と運用改善実践を支援する事業を開始し、その概要を公式サイトで紹介しています。
東京都の助成事業の対象者・対象設備は以下の通りです。
| 助成対象者 | 中小企業・公益財団法人・医療法人・社会福祉法人など/左記と共同で事業を展開するリース事業者・ESCO事業者 |
| 助成対象設備 | 高効率空調設備・LED照明設備などの省エネ設備導入/BEMS・照明スイッチ細分化工事などの運用改善 |
現状で上記の支援事業を行っているのは東京都だけですが、東京都をモデルに全国に広がる可能性が高い事業です。
東京都ほど大規模ではありませんが、日本政府と自治体からゼロエミッション推進事業を支援するための補助金を受け取れるので、企業がある自治体に問い合わせてみましょう。
(参考:東京都「省エネ設備導入・運用改善支援事業 助成開始」)
再生可能エネルギーの導入・利用
再生可能エネルギーの導入と利用でもゼロエミッションを開始できます。火力発電から再生可能エネルギーに切り替えた企業の具体例を見てみましょう。
| 実例 | 方法 |
| 使用電力の100%を実質CO2フリー化 | 本社・事業所の使用電力を再生可能エネルギー由来に転換 |
| CO2排出量100%削減 | 貨物船燃料を火力発電から水素に置き換え、船上に太陽光パネルを搭載したコンセプトシップを考案し、従来より70%のエネルギーを削減 |
| 再エネ主力電源化 | 再生可能エネルギー発電設備・蓄電池などの分散化した電源を統合・制御して大規模火力発電所のように稼働できるシステムを開発 |
| ゼロエミッション火力 | 火力発電で用いる石油・天然ガス焼却時にアンモニア・水素と混ぜ合わせてCO2排出量を削減(開発段階) |
また、廃棄物の再資源化などでゼロエミッションを達成している企業が増えています。ここで紹介した以外のさまざまな方法が考案されているので、ゼロエミッション推進中の企業のサイトをチェックしてみましょう。
まとめ
2050年カーボンニュートラル達成を目標にしているだけではなく、廃棄物の処理手段を課題にしている日本にとって、ゼロエミッションは非常に有意義な取り組みです。
資金面で難がある中小企業が取り組む際には補助金が支給されるメリットもあります。補助金の支給条件を政府や自治体の公式サイトで確認した上で取り組み計画を立てましょう。
お問い合わせ
サービスに関するご質問・相談など
お気軽にご相談ください。
担当よりご連絡いたします。
編集者
maeda